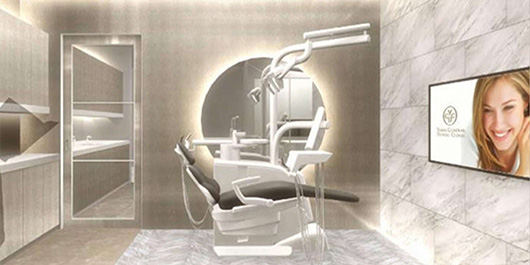お子さまの歯並びが気になる保護者の方は多いかと思いますが、実は歯並びはお口の中の問題だけでなく、全身のバランス、とくに姿勢と深く関係しています。
歯の生え方や噛み合わせは、顎の骨や筋肉の動きに大きく左右されるため、姿勢の悪さがそのまま歯並びに影響することもあるのです。
この記事では、子どもの歯並びと姿勢の関係性について解説するとともに、普段の生活の中で注意したい姿勢の癖や、保護者の方が気をつけたいポイントについて紹介します。
お子さまの将来の健康的な成長のためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次
■姿勢と歯並びはどうつながっている?
◎骨格と筋肉のバランスがポイントになる
歯並びは、顎の骨の成長と筋肉のバランスが影響しています。
人間の頭は体の上に乗っているため、姿勢が悪くなるとその影響が頭部、顎、口元にも及びます。
例えば、猫背になると頭の位置が前方にずれ、下顎も連動して前に出やすくなります。
これが続くと下顎が前方へ成長しやすくなり、受け口や開咬(かいこう)といった不正咬合の原因になることがあります。
また、体の左右バランスが乱れていると、片側の筋肉だけが発達して顎の成長が偏ってしまい、歯列が曲がったり、噛み合わせにズレが出たりすることもあります。
◎舌や口のまわりの筋肉の使い方にも影響
姿勢が悪いと、自然な呼吸や飲み込みの動作にも支障が出てきます。本来、舌は上顎に軽く触れる位置にあることが良いのですが、猫背などの悪い姿勢では舌の位置が下がりやすく、下顎側に落ちてしまうことがあります(低位舌)。
舌が下にあると、上顎の発育が不十分になり、歯がきれいに並ぶスペースが狭くなってしまいます。
これにより、叢生(そうせい)や八重歯など、歯並びがガタガタになる原因にもつながります。
■日常の姿勢にこんな癖があったら要注意
◎食事中に肘をついている
食事中に片肘をついて食べる癖があると、体の軸が傾いて顎の成長に偏りが生まれます。
また、片側だけで噛む癖がつき、噛み合わせにも影響があります。
◎テレビやスマホを見るときに顔が斜めになっている
椅子に深く座らず、背中を丸めて顔だけを前に突き出すような姿勢は、首から顎にかけての筋肉バランスを崩しやすく、顎のずれや、奥歯を噛み合わせた時に上下の前歯が噛み合わず隙間ができる「開咬(かいこう)」と呼ばれる歯並びを引き起こすことがあります。
◎イスに座ると足がブラブラしている
足が床につかずに浮いたままだと、体が安定せず、無意識のうちに姿勢が崩れます。
これが続くと顔や顎の成長にも影響し、歯並びが乱れる原因になります。
足の裏がしっかり地面につくイスの高さを調整したり、台を設けるなどして、床に足がつくように調節してあげましょう。
◎うつ伏せ寝や横向き寝が多い
就寝時の姿勢も顎の成長に関わってきます。
特にうつ伏せ寝や、いつも同じ方向を向いて寝ている癖があると、顎に継続的な力がかかり、左右差のある歯並びに発展することがあります。
■子どもの歯並びを守るために家庭でできること
◎正しい姿勢の習慣づけ
まずは日常生活の中で、正しい姿勢を保つよう声をかけていくことが大切です。
食事や読書、テレビを見るときなど、背筋を伸ばして椅子にしっかり座る習慣をつけましょう。
子どもが自分で意識できるよう、鏡や写真などを使って正しい姿勢を一緒に確認してみるのも良い方法です。
◎運動や遊びで全身のバランスを整える
姿勢は筋肉のバランスによって支えられているため、運動不足も姿勢の悪化につながります。
外遊びやバランスを使うような運動を積極的に取り入れることで、体幹が安定し、自然と姿勢も良くなっていきます。
◎歯科医院での定期的なチェック
歯が生え始める時期から定期的に歯医者でのチェックを受けることで、矯正治療が必要かどうか、必要なタイミングなどを提案してもらえます。歯並びに関して気になることがあれば定期検診などを利用して歯科医師に相談しましょう。
【姿勢を整えて健やかな歯並びを育てましょう】
子どもの歯並びの乱れには、遺伝だけでなく日常生活の姿勢も深く関係しています。
普段何気なく行っている姿勢が、顎の成長や歯並びに大きく影響していることを考えると、家庭での生活習慣を見直すことはとても重要です。
気になる姿勢の癖がある場合は、ぜひ歯科医院で相談してみてください。
子どもの頃に矯正しておくメリットについても解説していますので、あわせてご確認ください。